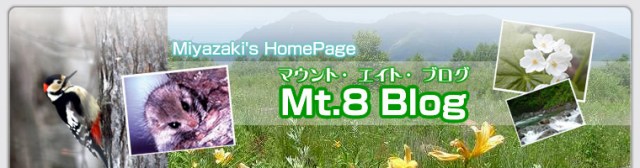東京都立墨田産院(閉院)で昭和33年4月に生まれた際、他の新生児と取り違えられた都内在住の江蔵(えぐら)智さん(67)=写真右=が都を相手取り、生みの親の調査義務があることの確認などを求めた訴訟で、東京地裁(平井直也裁判長)は21日、「出自を知る権利は憲法13条が保証する法的利益である」と判断して都に調査を命じる判決を言い渡した。
ブログ子は数十年前になるが日本で初めて赤ちゃん取り違え事件が発生した時第一報を発信した新聞記者である。この件は後述するが、以来多くの取り違え事件を取材してきたので原告の江蔵さんが訴訟を起こした時からカバーしてきたので、この判決が画期的な意味を持つと断言できる。同時に東京都は4年前に訴訟を起こされて以来頑なに情報開示を拒み続けたことが解せない。遅れた4年間で実の親は鬼籍に入ったかもしれないし、関係者への手づるも失われたかもしれないのだ。
一方で、江蔵さんは民事のほか損害賠償を求める訴訟も起こしていたがこの件では、既に平成18年の東京高裁判決で、都が産院の記録を調べたり、必要な調整をしたりしていたとして「調査義務の懈怠(けたい)があったとまではいえない」などとして退けている。こちらも見直す必要がある。
ほとんど報道されてこなかったので振り返る。
江蔵さんは幼少期から親族に、両親に似ていないといわれ続けた。平成9年に母親が入院したことがきっかけで、母親の血液型がB型と判明。父親はO型で、江蔵さんはA型と通常はありえない組み合わせだった。
16年にDNA型鑑定を行うと、親子関係は完全に否定された。考えられるのは、産院での取り違えだった。江蔵さんは住民基本台帳を使うなどして、誕生日の近い男性を探し歩いたが、取り違えの相手に出会うことはできなかった。いちるの望みをかけて令和3年、都には実の親を調査する義務があることを確認する訴訟の提起に踏み切った。
「生みの親に会えたら何と伝えたいか」。会見で問われた江蔵さんは時折言いよどみながら、こう絞り出した。「僕の口から何が出るか、お会いしてみないと何ともいえないです」
◇ ◇ ◇
今では、赤ちゃん取り違え事件というと沖縄で起きたケースを指すことが多い。1995年出版された 「ねじれた絆」-赤ちゃん取り違え事件の十七年(奥野修司著、文芸春秋社)という作品があるからだ。
しかし、我が国最初の「赤ちゃん取り違え事件」そのものは、これより以前に三重県で起きている。それも立て続けに2件も。 2件とも私がいた新聞社の四日市通信部の管内で起きた。
事件は昭和42年(1967)7月29日、四日市にある塩浜病院で、ついで8月6日少し山側に入った員弁郡の員弁厚生病院で起きた。現在、どこの病院でも生まれたばかりの赤ちゃんの足にタグがついているが、 それはこの事件の反省からで、それまでは、そんなことは起こるはずがないという前提で、産院では似たような赤ちゃんが並んで寝ていたものだ。
私は8月1日付で大阪社会部への異動の内示を受けていた。だから塩浜病院のケースでは送別会で飲み歩いて通信部に戻った夜10時ごろ、ある筋から知らされた。この地域に来る版の締め切りは9時半ですでに間に合わないがあわてて本紙用に叩き込んだ。翌日この地のブロック紙「中日新聞」がほぼ特ダネとして掲載していた。わが社の紙面には載っていないから「特オチ」(特ダネの反対)だ。
員弁厚生病院のケースは後任の記者が「特オチ」した。塩浜病院のケースは生後何か月だったからまだしも、員弁厚生病院のケースは2,3歳になっていたから、交換するときは双方の親にとって深刻な場面が生じたという。この報道がきっかけとなり、全国で再調査が行われて、この年だけで全国で4件の赤ちゃん取り違え事件が起きている。その後も続発していて、はっきりとした統計はないが、北海道から九州まで60数件はあるといわれている。
地方記者時代に体験した2件と各地で発生した取り違え事件については自分のホームページでも書いているので参考にしてほしい。ホームページ「八ケ岳の東から」→「ブン屋のたわ言」→「赤ちゃん取り違え事件」にあります。
巷間「氏より育ち」とか「実の親探しなどせず、知らないで過ごした方がいい」などという無責任な声もあるが、判決にあるように、「出自を知る権利は憲法が保障する法的利益である」という一点を理解することが枢要だ。